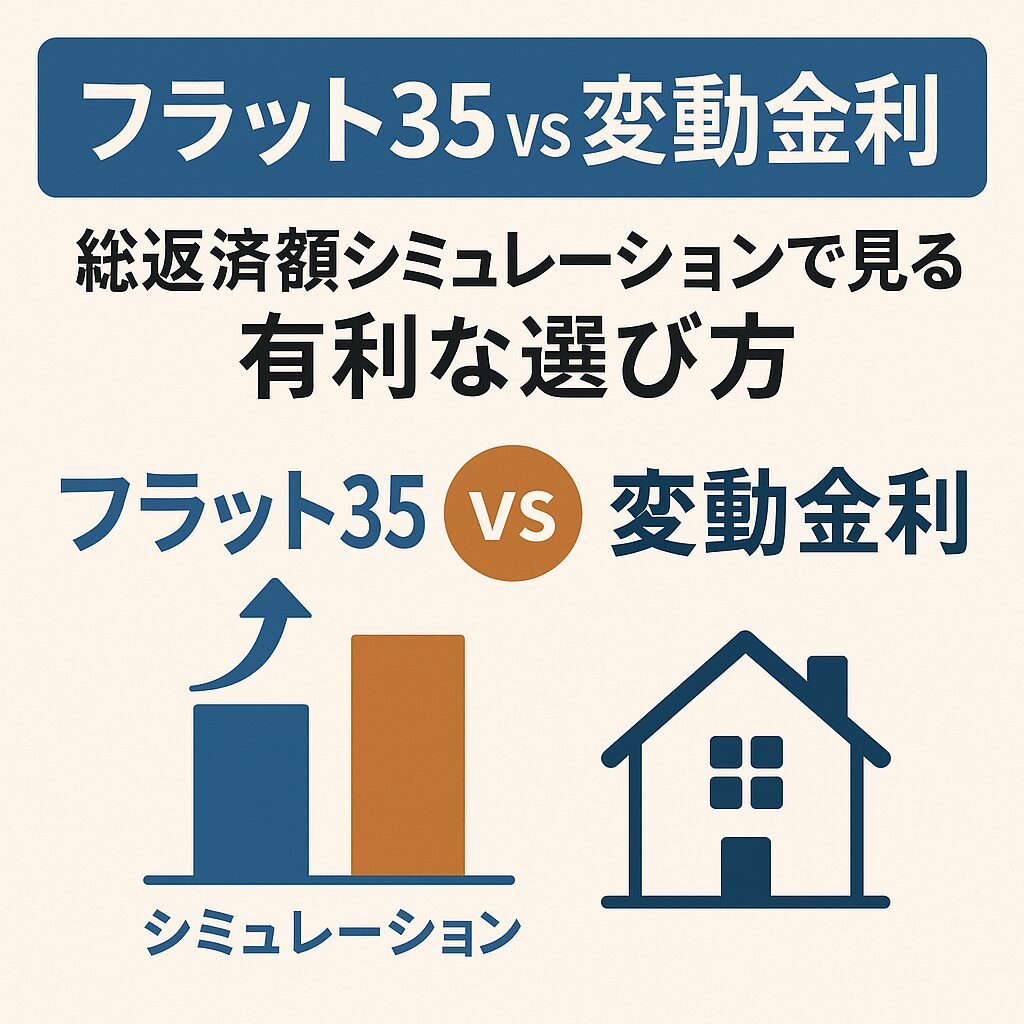
マイホームを購入する際、多くの人が頭を悩ませるのが住宅ローンです。
特に「フラット35(全期間固定金利型)」と「変動金利型ローン」は、どちらを選ぶかで数十年にわたる返済総額やライフプランが大きく変わります。
本記事では、両者の仕組みと特徴を整理した上で、現在の金利水準(2025年9月時点)を踏まえた具体的なシミュレーションを紹介します。
さらに、固定金利選択型やミックスローンなどの代替商品、そして金利見通しを考慮した複数パターンの検証の重要性についても解説します。
1. フラット35とは?
フラット35は、住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供する「全期間固定金利型ローン」です。借入時に決まった金利が完済まで変わらないため、将来の金利上昇リスクを完全に回避できます。
主な特徴
- 最長35年まで固定
- 返済額がずっと一定
- 繰上返済手数料が無料
- 耐震・省エネ性能を満たせば金利優遇(フラット35S)あり
メリット
- 長期にわたり返済計画が立てやすい
デメリット
- 変動金利より当初の金利が高め
2. 変動金利ローンとは?
変動金利型ローンは、半年ごとに金利が見直される商品です。
短期プライムレートに連動しており、当初は非常に低い金利で借りられるのが魅力です。
主な特徴
- 優遇後の金利は0.5〜0.7%程度(2025年9月現在)
- 返済額は「5年ルール」により5年間据え置き
- 上昇幅には「125%ルール」がある
メリット
- フラット35より当初の返済額が低い
デメリット
- 将来の金利動向次第で返済額が増える可能性あり
3. 現在の金利水準(2025年9月)
- フラット35:年1.89%(21年以上・融資率9割以下)
- 変動金利:年0.50〜0.70%台(優遇後)
現状では変動金利の方が圧倒的に低い水準ですが、今後の金利見通しによって有利・不利が変わります。
4. シミュレーション条件
- 借入額:4,000万円
- 返済期間:35年(元利均等返済)
- 繰上返済なし
5. シナリオ①:金利が上昇する場合(フラット35が有利)
- フラット35:1.89%固定
- 変動金利:当初0.60% → 10年後1.80% → 以降2.00%
試算結果(概算)
- フラット35:毎月返済 約12.2万円 → 総返済額 約5,692万円
- 変動金利:当初返済 約9.4万円 → 上昇後12万円超 → 総返済額 約6,000万円超
解説
当初は変動金利が有利ですが、10年以降の金利上昇で差が縮まり、最終的にフラット35の方が安定的かつ有利になる可能性があります。
6. シナリオ②:金利が低位安定する場合(変動金利が有利)
- フラット35:1.89%固定
- 変動金利:当初0.60% → 10年後も0.80〜1.20%
試算結果(概算)
- フラット35:総返済額 約5,692万円
- 変動金利:総返済額 約5,200万〜5,500万円
解説
低金利が長く続けば変動金利が圧倒的に有利です。
7. フラット35の優遇金利制度
「フラット35は高い」という印象を持つ方も多いですが、実際にはフラット35Sやフラット35子育てプラスなどの優遇制度があります。
併用も可能なので、当初5年から10年間で0.25~1%程度の金利優遇を受けることも可能です。
8. 固定金利選択型やミックスローンの選択肢
「固定か変動か」の二択ではなく、両者を組み合わせた商品もあります。
- 固定金利選択型:当初10〜15年を固定、その後変動へ移行
- ミックスローン:借入額を固定と変動に分け、リスクを分散
こうした商品を使えば、金利リスクを抑えつつ低金利の恩恵も享受できます。
9. 複数シナリオでシミュレーションする重要性
住宅ローンは35年に及ぶ長期契約です。
将来の金利を正確に予測することは誰にもできません。
だからこそ、複数のシナリオでシミュレーションを行うことが不可欠です。
ライフプラン(教育費・老後資金・転勤可能性など)と組み合わせて検討することで、自分に合ったローンが見えてきます。
10. どちらを選ぶべきか?判断のポイント
フラット35が向いている人
- 将来の返済額が変動することに不安を感じる
- 長期的に安定した返済計画を優先したい
- 金利上昇リスクを避けたい
変動金利が向いている人
- 当初の返済額を抑えたい
- 住み替えや繰上返済を予定している
- 金利上昇に対してリスクを取れる
まとめ
フラット35と変動金利ローンは、それぞれにメリットとデメリットがあります。
- 金利上昇局面ではフラット35が安心
- 低金利が続けば変動金利が有利
- フラット35の優遇金利制度や、固定選択型・ミックスローンといった選択肢も検討可能
- 複数の金利シナリオで試算することが失敗しないコツ
住宅ローンは単なる「金利比較」ではなく、ライフプラン全体と照らし合わせた最適化が重要です。不安があれば専門家に相談し、自分に合った形でマイホーム計画を進めていきましょう。
